「子どもにも自分にも勇気づけ」――勇気づけしあう学級づくりのすすめ2025年7月10日
【はじめに:教師のみなさまへ、教育に関心のある方へ】
このページを訪れてくださった先生方、教育関係者の方、そして教職を志す学生の皆さんへ。
ここに書かれているのは、「生徒たちをコントロールする」こと無く、生徒と教師、生徒と生徒、「互いに勇気づけしあう」ことを通じて、「つながっている思い」を育むためのささやかな提案です。

【鳴海さんが伝えたいこと】
この講座を続けてきたのは、カウンセラーとしての立場を通して、
教師のみな様が生徒との対応に苦慮した際に、「できることがたくさんあること。」を紹介したい、役立てていただきたいという思いからです。
鳴海さんは看護学校の非常勤講師を勤めたことや、また学校のゲストティーチャーを勤めたことがありますが、小中学校・高校の教職の勤務経験はありません。
営業職を23年、福祉職を10年弱経験し、アドラー心理学を中心に様々な療法などを学んでいます。中学校の「心の教室相談員」や部活指導において成果を上げてきました。
「教師が対応困難児に悩んでいる時、辛い思いをしている時、自分自身を勇気づけし、ストレス軽減を図り、怒りを伴うこと無く、子どもを支えるいろいろな方法があります。」
「いつも教師は子どもをよくしたいと思っています。」.そのやり方は子どもと生徒との相性がありますので、どの生徒にも一様に適用できるとは限りません。
ご本人は病気や事故のため、一時は車椅子状態になり、手足が不自由になりましたので、活動はほとんどできなくなりました。少しずつ回復するにつれ、家族や仲間の助けを借りながら、徐々に活動を再開しています。ゆっくりですが、確実に、歩みを続けています。
「身体は故障だらけですが、ハートと口は自由で元気です。」
と、常々言っています。
【つながっている思い(共同体感覚)は、学級づくりの基礎】
この講座が大事にしてきたものは、とてもシンプルです。
「つながっているという思い」が、子どもの心と体の居場所になる。」
「先生は味方だ。」「クラスメイトは仲間だ。」
「うれしい」「たのしい」
「ここは僕の居場所だ。」

【基本にある考え方ややり方】
鳴海さんの講座では、次のような理論や手法を土台にしています。

アドラー心理学の「共同体感覚」
と「勇気づけ」
つながっているという思い。自分を信じ、問題や課題と取り組む力を育む。

ロジャーズの「傾聴」
聴く力を育てる。

アサーション・
プレゼンテーション
伝える力を育てる。

コーチング
子ども自身が考える。教師も考える。

構成的グループエンカウンター
「みんな仲間だ」という体験を通じた人間関係づくり

学級会議~
オープンカウンセリング
役割もルールも民主的・主体的に決める。



子どもの権利条約からの視点
役割もルールも民主的・主体的に決める。
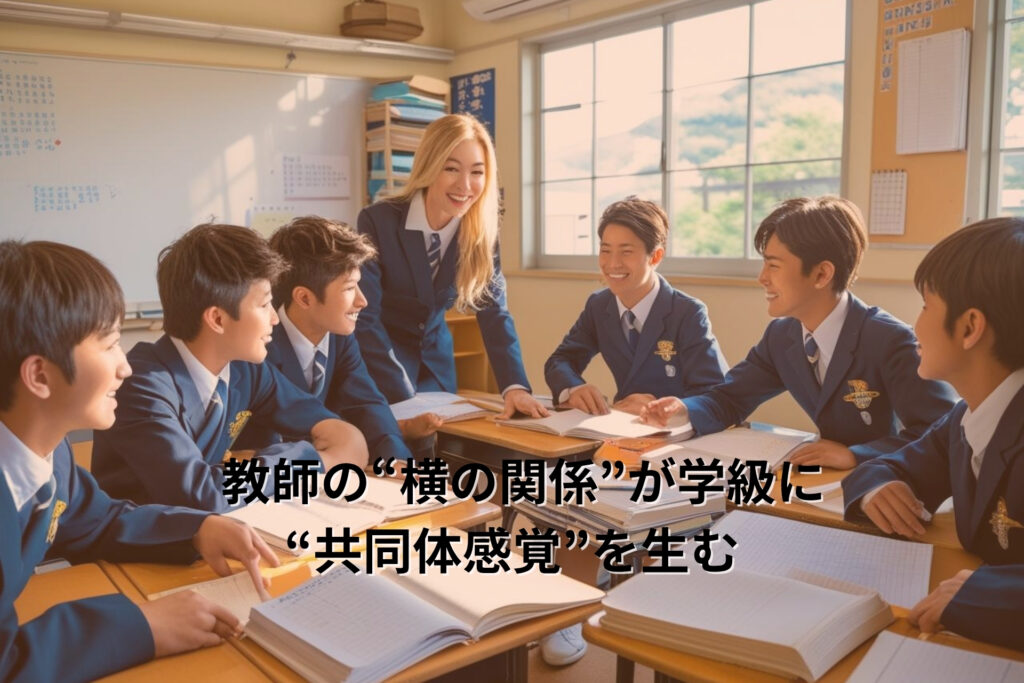

【教育課題に効果的な技法・手法】
近年、文部科学省の「生徒指導提要」でも、人間関係の質を重視する流れが示されています。
「心と体の居場所」づくりは、いじめや不登校の予防にも大きな成果が報告されています。
この講座の考え方は理想論ではなく、具体的な実践論です。

【カウンセラーから教師のみな様へのメッセージ】
鳴海さん自身は、教職勤務を経験していませんが、営業職(百貨店の売り場担当・保健の営業等)、福祉職(障害児・高齢者施設等)を経験し、数度の入院による医療現場での体験(現在も通院中)が豊富です。
だからこそ、現場で実践できることを大事にしてきました。
この講座は、教師を「指導する場」ではありません。
教師のみな様方が自分と仲間と互いに勇気づけしあい、学び合う場です。
【最後に:勇気づけし合う学校づくりへ】
特に管理職の教師の方が学校全体で取り組むことで、成果は目に見えて挙がります。
新任の教師、若手の教師だけで無く、ベテランの教師も一緒に取り組むことで、相乗効果が上がります。
一人で抱え込まず、相談できる職場の雰囲気づくりが大切です。
教師が傾聴し合う、伝え合う環境づくりが学級づくりにつながります。
そのための一歩を、この講座で一緒に考えてみませんか。
【参加を検討される皆さまへ】
落ち着かない学級、荒れる学級…協調的・自主的な学級に変わります。
子どもは話を聴いてくれない、話してくれない・・・傾聴とプレゼンテーションが役立ちます。
職員室の風通しをよくしたい。
教職を目指す学生の方
きっと具体的・実践的な役立つことがたくさん有ります。
子どもの保護者、教育に関心のある方、どなたの参加をも歓迎いたします。


下記申し込みフォームからお申込みいただけます。ご関心ある方からのご参加を心からお待ちしております。
2025教師の元気アップセミナー《勇気づけの学級づくり・生徒指導》運営事務局










